- ホーム
- ブログ
- 膝の離断性骨軟骨炎について|深谷市ふじ接骨院
そもそも、関節は部位により様々な形態と機能を持っていますが、基本的な構造として、骨の他に関節軟骨(かんせつなんこつ)、関節包(かんせつほう)、靱帯(じんたい)などから構成されます。 骨と骨が連結する部位の表面にはなめらかな関節軟骨が被っていて、これによって硬い組織である骨同士が直接ぶつかり合わないように、クッションのような役割をしています。
離断性骨軟骨炎とはこのクッションの役割をはたしている関節軟骨が繰り返されるストレスや外傷により軟骨下の骨に負荷がかかる事で血流障害により軟骨下の骨が壊死し骨軟骨片が分離、遊離し、痛みや関節の動かしづらさなどの症状があります。
発症部位として膝関節と肘関節に特に多く見られます。当ブログでは膝関節の離断性骨軟骨炎について主に深掘りしたいと思います。
診断は初期には通常のX線(レントゲン)で写り難いためMRI検査で確定診断します。
骨軟骨片が分離、遊離してくる時期はX線でも異常所見が出ますが、特殊な方向からのX線撮影も診断に有効です。

思春期から青年期(10~20歳代)に多く、性別では約2:1で男性に多く発症します。膝関節では大腿骨の内側が85%、外側が15%の頻度で、まれに膝蓋骨にも起こります。また、外側例では円板状半月(えんばんじょうはんげつ)を合併することもあります。スポーツ活動による膝の曲げ伸ばしを繰り返したり、捻ったりの動作を繰り返すと、成長期の骨軟骨の結合が弱いために、繰り返される外力や外傷によって軟骨下の骨に負担がかかるため発症します。

離断性骨軟骨炎の状態による分類
離断部位は形態と不安定性にしたがって分類されます。
非分離型(透亮期)
炎症が起きた骨軟骨がレントゲン画像で一部透けて見えます。

分離型
さらに症状が進んで、骨軟骨が母床から剥がれた状態です。

遊離型
骨軟骨が母床から完全に離れて、関節内で動いてしまう状態です。

遊離型にまで症状が進むと関節内の骨片を除去する手術が必要になります。
膝の離断性骨軟骨炎の症状
初期では、運動後の不快感や鈍痛の他は特異的な症状は出ません。しかし、症状が進み関節軟骨の表面に亀裂や変性が生じると疼痛も強くなり、スポーツなどで支障を来します。さらに、骨軟骨片が関節の中に遊離すると膝の曲げ伸ばしの際に引っかかり感やズレ感を生じ、関節に挟まると膝がロックして動かなくなってしまう所謂ロッキングが起きて日常生活にも支障が出てきます。
膝の離断性骨軟骨炎の治療法
若年者に対しては、明らかな離断や遊離体を認めない限りはまず保存的治療を試みます。
関節遊離体がある場合は外科的治療になりますが、当ブログでは保存的治療について記したいと思います。
保存的治療法
膝の離断性骨軟骨炎を発症すると、症状の段階にもよりますが疼痛や違和感により膝関節の動きが鈍くなってしまったり、ひどい時には膝の曲げ伸ばしが困難になり、日常生活に支障が生じます。保存的治療として、症状が軽微なものではスポーツ活動を中止し、痛みがなければレントゲン、MRIなどで経過を見ながら徐々にスポーツ復帰へと導きます。
症状が強い場合は、杖を用いて免荷とし、症状が軽快してくれば徐々に荷重をかけてもらいます。
スポーツ活動への復帰は全荷重可能となり徐々に進めていきますが、以前の競技レベルまで回復するには数カ月~1年くらい要します。保存的治療の原則は、活動性の低下を含めた生活指導と膝まわりの筋肉の筋力増強を行いながら、日常生活やスポーツ活動に復帰させることです。

大腿四頭筋のトレーニング方法
①背もたれのある椅子に深く腰掛けます
②片足をゆっくり水平まで持ち上げます
③5秒間キープします(息を止めながらすると血圧があがりとても危険です)してください。
④ゆっくりと元に戻します
⑤これを互いに2〜3回繰り返します。


大腿四頭筋のトレーニング方法その2
①ベッドに仰向けになり、膝の裏に丸めたタオルを入れます。
②そのタオルを潰すように膝を伸ばします
③5秒間キープします(息を止めながらすると血圧があがりとても危険です)してください。
④ゆっくりと元に戻します
⑤これを互いに2〜3回繰り返します。


①足を伸ばして座り、かかとの下にタオルを置きます
②かかとをゆっくりとお尻に近づけて、できるだけ膝を曲げます(息を止めながらすると血圧があがりとても危険です)
③かかとをゆっくりお尻から遠ざけて、できるだけ膝を伸ばします(息を止めながらすると血圧があがりとても危険です)
④これを互いに2〜3回繰り返します。


大腿四頭筋(太もも)のストレッチ
①ベッド仰向けになり伸ばしたい足を曲げます。
②右側を伸ばしたい場合は右手で右足を引き上げ、右足のつま先をお尻の方へ引き寄せてください。(息を止めながらすると血圧があがりとても危険です)。
③そのまま10秒程キープします。
④反対側の足も同じようにストレッチします。

大腿四頭筋(太もも)のストレッチその2
①壁に手をつき伸ばしたい方の足をつかみます。
②そのまま10秒程キープします。
③反対側の足も同じようにストレッチします。


体重をかけられるような段階になってきたらウォーキングによるリハビリも重要になってきます。
ウォーキングによる全身運動により膝まわりの筋肉だけでなく全身の筋肉を使うことで少しずつ競技に復帰する体力作りになります。
①背筋を伸ばし、軽くお腹を引き締めて歩く。
②腕を足の動きに合わせて自然に振る。
③歩幅は、足を着地するときに膝が軽く曲がる程度にとる。
④拇趾(つま先)で地面を蹴る。
⑤かかとから着地する。

当院では、まずお話を伺った後に視診・触診・検査等を行い、その症状に合わせた治療を提案し、施術させて頂きます。
症状に合わせた治療を提案させて頂くのに以下の治療を中心に行っております。
1つ目は、筋肉に対して、刺激を与え、血流の流れを良くし、回復力を高めて上げる「筋治療」を施術します。

2つ目は、骨盤のゆがみを矯正し、身体のバランスを整え、神経・血流の流れを良くして、回復力を高める「骨盤矯正」を施術します。
当院では、アジャスターという器具を使用し、矯正するため、身体の負担を少ない状態で受けれるため、年齢問わず施術出来ます。

3つ目は、痛みが出ている場所のツボや治療点を見つけ、鍼をさして微電流を流すことによって血行を良くして筋の緊張を緩める「鍼治療」を施術します。また、鍼を刺すことで痛みを感じる限界値を上げて痛みを感じにくくなるように促します。

当院の鍼治療で使用する鍼は細い鍼を使用し、施術する為、少ない痛みで施術出来ます。
4つ目は、痛みがある部分に対して、より深い刺激を与えて、身体の回復力を高め、早く痛みを改善出来るようにする「超音波治療」を施術します。

こちらは「EU-910」という機械を使用して、施術します。
膝の離断性骨軟骨炎を発症した時には
①スポーツ活動の中止。
②膝まわりの筋肉のトレーニングを行う。
③マッサージなどで膝まわりの筋肉を緩める。
④膝に負担のかからない体重管理。
をすることが重要になってきます。膝の離断性骨軟骨炎はスポーツ活動をする思春期から青年期(10~20歳代)に多い症状です。主に関節内の軟骨に繰り返し刺激が加わることで発生するため、一度の外傷のように症状が即、現われるわけではありません。普段からスポーツ活動後のケアが大事になります。膝まわりの筋肉の強化やストレッチをすることで膝への負担を軽減させることを意識してください。症状が初期なものでは疼痛などは一時的なものでそのうちに落ち着くだろうと思い我慢してしまうと重症化したり、治療期間が長引き競技に復帰できるまで時間がかかります。焦る気持ちを抑えつつ、症状の緩和を目指していくことが大事になります。
ふじ接骨院・鍼灸院では、深谷市・籠原エリアを中心に、お客様一人一人に合わせた施術を心がけています。
スポーツをしていて起きてしまった外傷や交通事故での治療など幅広く対応させていただきます。
また日常で起こる肩や腰などの慢性的な痛みがある方もアットホームな雰囲気の当接骨院にぜひお気軽にご相談いただければと思います。
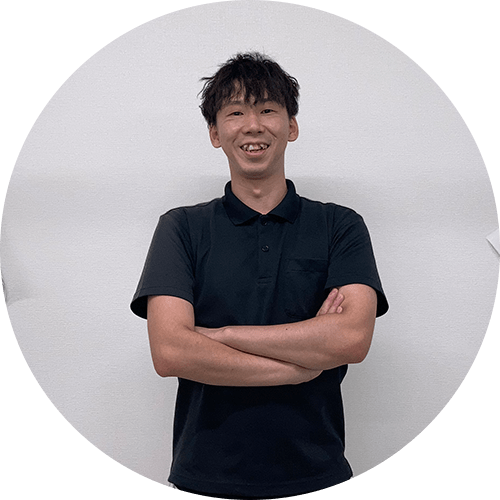
1986年6月24日 AB型
趣味:サッカー観戦、ゴルフ
資格:柔道整復師